- 公開日:2025/11/28
- 最終更新日:2025/11/28
建築プロジェクトを成功へと導く鍵となるのが、明確な「建築コンセプト」です。一見すると抽象的に思えるこの概念は、設計の方向性を定め、意思決定を統一し、最終的に建物の価値を最大化するための羅針盤となります。経営者や施設責任者として建築設計を依頼する際、このコンセプトの有無が投資対効果を大きく左右することをご存知でしょうか。
この記事では、建築コンセプトの定義から実務での作り方、成功事例と失敗例までを詳しく解説します。

建築コンセプトの定義と役割
建築コンセプトは、建築プロジェクト全体の方向性を定める「思想的な設計軸」です。単なるデザインテーマではなく、空間構成・素材選定・動線計画・コスト配分など、あらゆる設計判断の拠り所となります。明確なコンセプトを持つことで、プロジェクトは一貫性を保ち、機能性と美しさを両立した建築へと導かれます。
建築コンセプトとは
優れた建築コンセプトは、抽象的すぎず具体的すぎず、プロジェクトの独自性を際立たせながらも実現可能な範囲に収めるバランスを持っています。たとえば「美しい建物」では曖昧すぎますが、「患者の回復を促進する癒しの光環境を持つ医療施設」であれば、設計意図が明確になり、照明計画や窓配置、素材選定といった具体的な設計判断へと落とし込むことができます。
建築コンセプトは、クライアントのビジョン、敷地条件、予算制約、法規要件、利用者ニーズなど多様な要素を統合し、一貫性のある建築テーマへと昇華させたものです。この過程で重要なのは、単に機能を満たすだけでなく、建物がもたらす体験価値やビジネス上の効果まで見据えることです。
建築コンセプトが設計プロジェクトにもたらす効果
明確な建築コンセプトを持つことで、設計プロセス全体に複数の重要な効果がもたらされます。第一に、意思決定の迅速化と一貫性の確保が挙げられます。設計段階では数え切れないほどの選択肢が生まれますが、コンセプトという判断基準があれば、それに照らして適切な選択を素早く行えます。
第二に、ステークホルダー間のコミュニケーション効率が飛躍的に向上します。建築プロジェクトには建築家、構造設計者、設備設計者、施工者、行政、そしてクライアント企業内の複数部門など多くの関係者が関わります。共通のコンセプトがあることで、それぞれの専門領域での判断がプロジェクト全体の方向性と矛盾しなくなり、手戻りや調整コストを大幅に削減できます。
第三に、プレゼンテーションやマーケティングにおける説得力が増します。意思決定を行う人々に対し、建築コンセプトは「なぜこの設計が最適なのか」を論理的に説明する強力なツールとなります。単なる平面図や立面図の羅列ではなく、ビジネス戦略と結びついた建築の方向性を示すことで、承認プロセスがスムーズになります。
- 設計判断の迅速化と一貫性の維持
- ステークホルダー間のコミュニケーション効率化
- プレゼンテーション・マーケティングでの説得力向上
- コスト配分の最適化と投資対効果の明確化
- 竣工後の運用方針やブランディングとの一貫性確保
さらに、建築コンセプトはコスト配分の最適化にも寄与します。限られた予算をどこに重点配分すべきかを決める際、コンセプトに照らして優先順位を明確にできます。たとえば「顧客体験の質を最大化する商業施設」というコンセプトであれば、エントランスや顧客動線に関わる部分に予算を重点配分し、バックヤードは必要最小限に抑えるという判断が合理的になります。
建築コンセプトと法規や予算や用途の関係
建築コンセプトは、法規制・予算制約・用途要件という三つの現実的制約と密接に関係しながら形成されます。これらは決してコンセプトを制限する障壁ではなく、むしろ独自性を生み出す創造的な条件として捉えるべきです。
法規制との関係では、建築基準法や消防法、バリアフリー法などの法的要件を満たしながらも、それを単なるチェックリストとして扱うのではなく、コンセプトに統合する視点が重要です。たとえば避難経路の確保という法規要件を、「日常動線と緊急動線が自然に融合した安心感のある空間」というコンセプトに昇華させることで、法規遵守と設計意図が矛盾しない統合的な解決策が生まれます。
予算との関係では、建築コンセプトは投資の意味づけを明確にします。単に「坪単価○○万円で建てる」という数値目標ではなく、「投資対効果を最大化する空間価値の創出」といったコンセプトレベルでの目標設定が、VE(バリューエンジニアリング)提案の質を高めます。コスト削減が必要な局面でも、コンセプトの核心部分を守りながら代替案を検討できるため、価値を損なわない最適化が可能になります。
用途要件との関係では、建築コンセプトは要求される機能を超えた付加価値を定義します。たとえば病院であれば「医療機能を満たす」のは当然の前提ですが、そこに「患者の回復を促進する環境」「スタッフの働きやすさを高める動線」「地域に開かれた健康拠点」といったコンセプトを加えることで、単なる箱としての建物から、ビジネス戦略や社会的使命を体現する施設へと昇華します。
敷地条件も同様に、建築コンセプトを形成する重要な要素です。狭小地、変形地、斜面地といった一見不利な条件も、適切なコンセプト設定によって独自の魅力へと転換できます。「制約を個性に変える」という視点こそが、建築コンセプトの創造的な側面です。
| 制約条件 | コンセプトとの関係 | 実務での活用例 |
|---|---|---|
| 法規制 | 遵守すべき基準をコンセプトに統合 | 避難動線を日常動線と調和させたデザイン |
| 予算制約 | 投資優先順位を決定する基準 | 顧客接点空間への重点配分 |
| 用途要件 | 機能を超えた体験価値の設定 | 医療機能と癒し環境の両立 |
| 敷地条件 | 制約を個性に転換する視点 | 狭小地を「親密な空間体験」に昇華 |
建築コンセプトの作り方
建築コンセプトは一朝一夕に生まれるものではなく、体系的なプロセスを経て練り上げられます。ここでは実務で使える具体的な手法を、段階を追って解説します。
目標設定とヒアリングで決める
建築コンセプト構築の第一段階は、クライアントの本質的なニーズと目標を深く理解することです。ここで重要なのは、表面的な要望だけでなく、その背景にあるビジネス戦略や組織文化、将来ビジョンまで掘り下げることです。
効果的なクライアントヒアリングでは、単に「何室必要か」「予算はいくらか」といった定量的な情報だけでなく、定性的な情報を引き出すことが重要です。たとえば「なぜ今この建築プロジェクトが必要なのか」「この建物を通じてどのような変化を実現したいのか」「10年後、この建物がどう使われていることを期待するか」といった問いかけが有効です。
経営者や理事長との対話では、建物単体ではなく、ビジネスモデル全体における建築の位置づけを確認します。商業施設であれば売上目標や顧客層、病院であれば診療方針や地域での役割、オフィスであれば働き方改革の方向性や採用戦略などです。これらのビジネス要件を建築計画に翻訳することで、機能的要求だけでなく、戦略的価値を持つコンセプトが形成されます。
また、ステークホルダーマップを作成し、建物に関わる多様な利害関係者(利用者、訪問者、スタッフ、近隣住民など)のニーズを整理することも重要です。それぞれのニーズには優先順位をつけ、時に矛盾する要求をどうバランスさせるかを検討します。この過程自体が、建築コンセプトの核心を見出す作業となります。

敷地と周辺環境を踏まえたコンテクスト分析
建築コンセプトは、敷地とその周辺環境というコンテクストと切り離せません。敷地の物理的特性(形状、高低差、方位、隣接条件など)と、社会的・文化的特性(地域の歴史、周辺の建物、街の文脈など)の両面から分析を行います。
物理的な敷地分析では、日照・通風・眺望といった環境要素を詳細に調査します。これらは単なる条件整理ではなく、建物の空間構成を決定づける要素です。たとえば南側に良好な眺望があれば「眺望を最大限に活用した開放的な空間」、北側斜面であれば「地形に寄り添う段状の空間構成」といったコンセプトの方向性が見えてきます。
周辺環境との関係性も重要です。建物が街並みにどう貢献するか、既存の都市構造をどう読み解くかという視点が、建築コンセプトに深みを与えます。歴史的な街区であれば「伝統と現代の対話」、新興開発地域であれば「新しいコミュニティの核となる場」といったテーマが考えられます。
- 敷地の形状・面積・高低差・地質条件
- 日照・通風・眺望などの環境要因
- 周辺の建物の高さ・用途・建築様式
- 主要な街路や公共空間との関係
- 地域の歴史的・文化的背景
- 将来的な都市計画や開発動向
- 近隣住民や地域コミュニティとの関係
法規制の分析もこの段階で行います。用途地域、容積率、高さ制限、日影規制などの制約を把握し、それらを単なる制限としてではなく、コンセプトを形成する条件として捉えます。たとえば厳しい高さ制限がある場合、「水平に広がる親密なスケール感」といったコンセプトに転換できます。
さらに、気候条件や自然災害リスク(地震、水害、台風など)も考慮に入れます。これらは安全性確保という技術的要件であると同時に、「自然と共生する建築」「レジリエントな施設」といったコンセプトレベルのテーマにもなり得ます。
アイデア発想からキーワード化する手法
クライアントヒアリングと敷地分析から得られた情報をもとに、具体的なアイデア発想とコンセプト化のプロセスに入ります。ここでは、抽象的な思考と具体的な検討を行き来しながら、本質的なキーワードへと収斂させていく作業が求められます。
まずブレインストーミングで可能な限り多くのアイデアを出します。この段階では批判や評価を避け、自由な発想を重視します。クライアントの言葉、敷地の特徴、建築の用途、将来のビジョンなど、あらゆる要素から連想されるイメージ、メタファー、キーワードをリストアップします。
次にこれらのアイデアを分類・統合し、いくつかのコンセプト候補へと絞り込みます。この過程では、単に印象的な言葉を選ぶのではなく、プロジェクトの本質を捉え、かつ実現可能性のあるものを選別します。優れた建築コンセプトは、詩的でありながら論理的であり、抽象的でありながら具体的な展開可能性を持っています。
コンセプトを言語化する際は、短く印象的なキーフレーズと、それを補足する説明文の両方を用意します。キーフレーズは関係者全員が記憶できる簡潔なもの(10語以内が理想)で、説明文ではそのコンセプトが何を意味し、どのような空間や体験につながるかを明確にします。
- ブレインストーミングで自由なアイデア出し(30-50個)
- アイデアの分類とグルーピング(5-10のテーマに集約)
- プロジェクトの本質に照らした評価と絞り込み(3-5候補)
- キーフレーズと説明文の作成
- クライアントとの対話による検証と調整
- 最終的なコンセプトステートメントの確定
コンセプトモデルの作成も有効です。簡単なスケッチやダイアグラム、コラージュなどで視覚的にコンセプトを表現することで、言葉だけでは伝わりにくいニュアンスや空間イメージを共有できます。この段階では完成度の高い図面は不要で、むしろラフなスケッチの方がアイデアの柔軟性を保てます。
複数のコンセプト候補が出た場合は、それぞれについて「この建物の成功をどう定義するか」「10年後にどう評価されたいか」という観点から評価します。クライアントとの対話を重ねながら、最も本質的で実現可能性の高いコンセプトへと収斂させていきます。
コンセプトを図面や模型や素材で具体化する方法
言語化された建築コンセプトは、図面、模型、素材サンプルなどの具体的なツールを通じて、設計チームとクライアントの共通理解へと落とし込まれます。この具体化のプロセスが、コンセプトを実際の建築へと変換する重要なステップです。
初期スケッチや概念図では、空間の基本的な構成原理をコンセプトと結びつけて示します。たとえば「内外の連続性」というコンセプトであれば、大開口や中間領域(テラス、庇下空間など)を強調したダイアグラムを描きます。この段階では細部よりも全体の骨格を示すことが重要です。
スタディ模型は、三次元での空間体験をシミュレートする強力なツールです。特に経営層や非専門家に対しては、図面よりも模型の方が直感的に理解されやすいため、初期段階から積極的に活用すべきです。模型のスケールや詳細度は目的に応じて変えますが、コンセプト検討段階では、細部を省略したボリューム模型や、特定の空間に焦点を当てた部分模型が有効です。
素材やカラーサンプルも、コンセプトの質感を伝える重要な要素です。「温かみのある医療空間」というコンセプトであれば、木材やナチュラルな質感を感じさせる素材を示し、「先進的な企業イメージ」であればガラスや金属などの素材を提案します。素材は単なる仕上げではなく、空間の雰囲気を決定づける要素として、コンセプトと密接に関連づけて提案します。
プレゼンテーションボードやコンセプトブックの作成も効果的です。コンセプトステートメント、参考イメージ、スケッチ、模型写真などを一つのストーリーとして編集し、プロジェクトの全体像を視覚的に伝えます。特に理事会や投資判断の場では、技術的な図面よりも、ビジョンと戦略を明確に示すこうした資料の方が説得力を持ちます。
デジタルツールの活用も進んでいます。BIM(建物情報モデリング)を使えば、設計の初期段階から三次元モデルで検討でき、空間の連続性や光の入り方などをシミュレートできます。ただし、ツールに振り回されず、あくまでコンセプトを具体化するための手段として位置づけることが重要です。
| ツール | 適した用途 | 作成のポイント |
|---|---|---|
| ダイアグラム | 空間構成の基本原理の説明 | シンプルで直感的な図式化 |
| スケッチ | 空間イメージの共有 | 雰囲気を伝える描写力 |
| ボリューム模型 | 全体構成の検討 | 周辺環境との関係を含める |
| 内観模型 | 空間体験のシミュレーション | 人のスケール感を意識 |
| 素材サンプル | 質感と雰囲気の伝達 | 実際の使用状況に近い形で提示 |
| CG・BIM | 詳細なビジュアル検討 | 光や視点の設定を慎重に |
これらの具体化ツールは、設計プロセス全体を通じて段階的に詳細化されていきます。初期段階では大まかな方向性を示し、基本設計では空間構成の具体化を、実施設計では仕上げや設備まで含めた総合的な表現へと発展させます。各段階でコンセプトとの整合性を確認し、必要に応じて調整を加えることで、最終的な建築が当初のコンセプトを体現したものとなります。
建築コンセプトの実例と注意点
優れた建築コンセプトは、理論だけでなく実践の中で磨かれます。ここでは実際のプロジェクト事例から学ぶべき要点と、実務で陥りがちな失敗パターンを解説します。
事例紹介:コンセプトの徹底による非日常体験の創出(CLOUD OF LUSTER CHAPEL)
CLOUD OF LUSTER CHAPEL の事例を用いて、コンセプトが非日常的な体験価値、コスト最適化、機能設計にどのように影響するか詳しく見ていきましょう 。

■ プロジェクトの要点
- コンセプト:水盤に浮かぶ「雲」をイメージしたシームレスな空間体験 。新郎新婦にとって特別な日を、より特別な日にする非日常的な風景を追求
- 形態と素材:輪郭は全て曲線で描かれ、曲面ガラスが空間を包み込む 。床面は透明なガラスビーズを樹脂で固め、日差しで水盤のようにキラキラと光る演出
- コスト戦略:特殊な曲面ガラスやステンレスサッシの制作コストを抑えるため、軌跡の半径を2500ミリに規格化
- 機能統合:天井に一切の設備を配置せず、照明や空調吹出口は全て床面に設置することで、空間を覆う雲を淀みのないものにした
- 名称と象徴性:新郎新婦の門出の象徴として、エル・ブランシュ(白い翼)と名付けられた
| 体験価値(美) | 「雲」という詩的なコンセプトを曲線構成と床面演出で具現化し、記憶に残る非日常的な体験を創出 。 |
|---|---|
| 機能統合(用) | 「雲」というデザインを邪魔しないよう、照明・空調を床に隠すことで、機能性と美観を両立 。 |
| コスト管理(強) | 特殊な曲面デザインにもかかわらず、曲面半径の規格化という工夫で、制作精度とコスト最適化を実現 。 |
成功事例に見るコンセプトの要点
成功事例に共通するのは、明確なコンセプトが建物のあらゆる側面に一貫して反映されている点です。単なる装飾的なテーマではなく、空間構成、動線計画、素材選定、照明計画、ランドスケープに至るまで、すべてがコンセプトから論理的に導き出されています。
ある医療施設の事例では、「患者中心の癒しの環境」というコンセプトが掲げられました。これを実現するため、待合空間に自然光を豊富に取り入れる大開口を設け、室内に中庭を配置し、診察室への動線に圧迫感を与えない天井高を確保しました。さらに、木材や植栽を積極的に用いることで、病院特有の無機質な印象を払拭しています。このプロジェクトでは、患者満足度調査で高評価を得ただけでなく、スタッフの働きやすさも向上し、離職率の低下という経営面での効果も確認されました。
商業施設の事例では、「地域とつながる開かれた広場」というコンセプトが成功を収めています。従来の閉鎖的なショッピングセンターではなく、周辺の街路と連続する半屋外空間を設け、テナント店舗も街に対して開放的な構えとしました。この結果、単なる買い物客だけでなく、近隣住民が日常的に立ち寄る場となり、稼働率と売上が当初予測を上回りました。建築コンセプトがビジネス戦略と直結した好例です。
オフィスビルの事例では、「創造性を刺激するコラボレーション空間」というコンセプトが特徴的です。固定席を減らし、多様な働き方に対応するフリーアドレスエリア、偶発的な出会いを生む共用ラウンジ、集中作業のための個室ブースなど、用途の異なる空間を意図的に配置しました。このコンセプトは採用活動でも強力なアピールポイントとなり、優秀な人材の獲得に貢献しています。建築が人事戦略を支援する例です。
- クライアントのビジネス目標と明確にリンクしている
- 利用者の体験価値を具体的に定義している
- 敷地やコンテクストの特性を活かしている
- 細部に至るまで一貫してコンセプトが反映されている
- 定量的な効果(売上、満足度、採用力など)で検証可能
- 竣工後の運用やブランディングにも継続的に活用されている
これらの成功事例に共通するもう一つの要素は、コンセプトの評価が竣工後も継続的に行われていることです。利用者アンケート、売上データ、稼働率などの定量的指標と、利用者の行動観察や満足度といった定性的評価を組み合わせて、コンセプトが実際に機能しているかを検証しています。この検証プロセス自体が、次のプロジェクトへの学びとなり、組織の設計力を高めていきます。
よくある失敗例と実務での回避策
一方で、建築コンセプトの扱いを誤ると、プロジェクト全体が迷走する原因となります。最もよくある失敗は、「抽象的すぎるコンセプト」です。「人に優しい」「未来志向」「調和」といった美辞麗句は聞こえは良いものの、具体的な設計判断に結びつきません。このようなコンセプトでは、設計チーム内でも解釈が分かれ、一貫性のない建築が生まれてしまいます。
回避策としては、コンセプトステートメントに具体的な設計方針や優先順位を必ず含めることです。「人に優しい」ではなく「高齢者が自立的に移動できるバリアフリー動線と、自然光による明るい空間」といったように、実現すべき具体的な状態を記述します。また、コンセプトから導かれる設計原則をリスト化し、判断基準として共有することも有効です。
第二の失敗は、「コンセプトとクライアントニーズの乖離」です。建築家が独自のアイデアに固執し、クライアントの本質的な要求やビジネス目標を無視したコンセプトを押し付けると、プロジェクトは必ず行き詰まります。芸術作品としての建築を追求するあまり、使い勝手や経済性を軽視する例が少なくありません。
これを避けるには、コンセプト形成の初期段階からクライアントを深く巻き込むことです。ヒアリングを一度で終わらせず、継続的な対話を通じてニーズを掘り下げます。また、コンセプト案を複数提示し、それぞれのメリット・デメリットをビジネス面も含めて説明することで、クライアント自身が納得できる選択を支援します。
第三の失敗は、「設計途中でのコンセプト変更」です。初期段階で決めたコンセプトが、基本設計や実施設計の段階で無視され、場当たり的な判断が積み重なることで、最終的に何を目指していたのか分からない建築になってしまいます。これは特に、多数のステークホルダーが関わる大規模プロジェクトで起こりがちです。
回避策としては、プロジェクトの節目ごとに「コンセプト確認会議」を設定し、設計案が当初のコンセプトを体現しているかをチェックします。もしコンセプトの修正が必要であれば、その理由を明確にし、関係者全員で合意した上で変更します。場当たり的な変更ではなく、意図的な進化としてコンセプトを扱うことが重要です。
第四の失敗は、「実現不可能なコンセプト」です。予算や技術的制約、法規制を無視した理想論だけでコンセプトを設定すると、後に大幅な設計変更を余儀なくされ、時間とコストを浪費します。特に初期段階での楽観的な見積もりが、プロジェクト後半で深刻な問題を引き起こします。
これを防ぐには、コンセプト設定の段階から、概算コストや技術的実現性を並行して検討します。構造設計者や設備設計者、コストコンサルタントを早期に参画させ、多角的な視点でコンセプトの妥当性を評価します。もし技術的なチャレンジが必要であれば、それをリスク要因として明示し、代替案も準備しておきます。
最後に、「コンセプトの形骸化」という問題もあります。初期段階では熱心に議論されたコンセプトが、プロジェクトが進むにつれて誰も参照しなくなり、単なる飾りの言葉になってしまうケースです。これでは、コンセプトを設定した意味がありません。
これを防ぐには、コンセプトを常に視覚化し、チーム全員が共有できる場所に掲示します。会議の冒頭でコンセプトを確認する習慣をつけたり、設計判断の際に「このアイデアはコンセプトに合致しているか」を問いかける文化を作ることも有効です。コンセプトを生きた指針として扱い続けることが、一貫性のある建築を生み出す鍵です。
| 失敗パターン | 問題点 | 回避策 |
|---|---|---|
| 抽象的すぎるコンセプト | 設計判断の基準にならない | 具体的な設計方針と優先順位を明記 |
| クライアントニーズとの乖離 | ビジネス目標が達成できない | 継続的な対話と複数案の提示 |
| コンセプトの途中変更 | 一貫性が失われる | 初期段階での十分な検討と合意形成 |
| 実現不可能なコンセプト | 予算・技術的に破綻 | 早期の技術検証とVE提案 |
| コンセプトの形骸化 | 設計途中で忘れられる | 定期的なコンセプト確認の機会設定 |
まとめ
この記事では、建築コンセプトの本質的な意味から、具体的な作り方、成功事例と失敗例までを詳しく解説してきました。建築コンセプトは単なる装飾的なテーマではなく、プロジェクト全体を貫く中心思想であり、すべての設計判断の基準となる重要な要素です。明確なコンセプトを持つことで、意思決定の迅速化、ステークホルダー間のコミュニケーション効率化、投資対効果の最大化が実現されるでしょう。
「商業建築の設計は、ただ美しい箱を作りだすためのプロセスであってはならない。」というのが、私達KTXの考え方です。
より大きなベネフィットを生む建築を創り出し、投資に見合う利益を還元するビジネスツールを我々は設計しています。建築設計からインテリアの空間デザイン、グラフィックに至るまで、あらゆるデザインを一貫してコントロールすることであなたのビジネスに強力な付加価値を生み出します。もし、建築設計についてお悩みなのであれば、是非一度我々にご相談ください。
KTXアーキラボでは、ご意向に沿う設計コンセプトをご提案しております。お気軽にお問い合わせください。
2025.11.28

【この記事を書いた人 松本哲哉】
KTXアーキラボ代表・一級建築士・大阪芸術大学非常勤講師
2024年度イタリアDAC認定デザイナーランキング世界8位(日本国内1位)
【お問い合わせ先】
KTXアーキラボ一級建築士事務所
東京都港区南麻布3-4-5 エスセナーリオ南麻布002
兵庫県姫路市船丘町298-2 日新ビル2F
事業内容
飲食店・クリニック・物販店・美容院などの店舗デザイン・設計
建築・内装工事施工
メール:kentixx@ktx.space
電話番号:03-4400-4529(代表)
ウェブサイト:https://ktx.space/
【関連記事リンク】
コメントを投稿するにはログインが必要です。
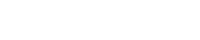




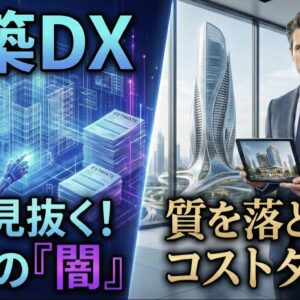
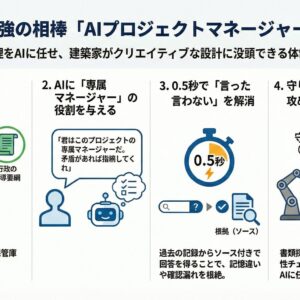
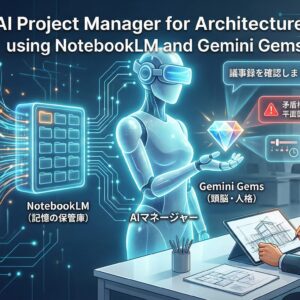
コメントを投稿するにはログインしてください。